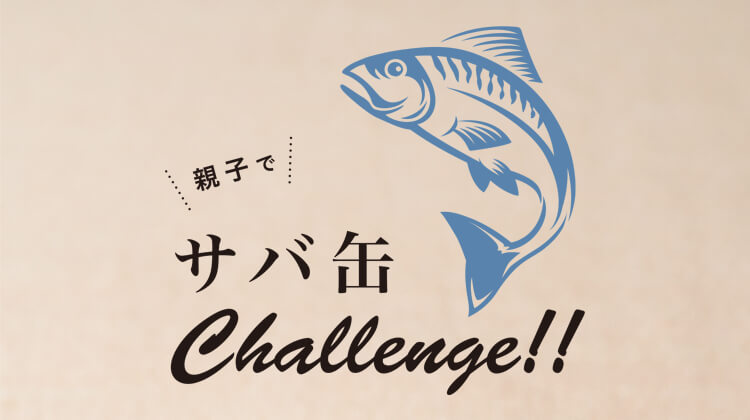2021.04.20 取材
酢と共に神の仕え八咫烏の導きをたどる
特集
蔵元 中野商店

-
京都の中心部から鴨川沿いを北に上がっていくと京都が誇る世界遺産「上賀茂神社」が見えてくる。その世界遺産の近くにある商店街を歩いていくと、静かにたたずむ小さなお店が見えた。
このお酢屋さんの名は蔵元中野商店。お店に掛かる臙脂色の暖簾をくぐると、少し値段が高めなお酢が並んでいた。それらが後世に残していかなければいけない国宝級のお酢たちだということを、私は後々知ることになる。
[文:木下裕美子]
語り継がれる礎
蔵元中野商店は創業1639年。
約380年近く続く中野商店は、「本物を後世に伝える」という想いを持ち続け、創業当時から変わらない正しい製法でお酢を造り続けている。
中野商店の醸造蔵は、三重県最南端に位置する南牟婁郡紀宝町の世界遺産「熊野古道」の付近にある。その土地は高温多湿の自然環境に恵まれた発酵醸造のお酢を造るのに最適な場所である。
蔵には、男性の背丈より高い木の桶が100本以上ひしめき合っている。古いものでは徳川の時代から残っているものもあるようだ。
しかし、そんな歴史のある木桶を持っている蔵元は、現在、同じお酢の業界でもほとんど残っていない。それどころか、日本には数件しか木桶でお酢を造っているところが残っていない。ステンレスの桶などの方がメンテナンスも簡単で、大量にお酢の生産ができるため、時代と共に変えていく醸造元も多かったようだ。しかし、中野商店は時間も手間もかかり、人手も多くいる「木桶仕込み」「静置発酵法」という昔ながらの製法を変えることなく続けている。
そこには、どんなに技術が発達しても人の力ではどうにもできない自然の恩恵で育てあげてきた菌たちが存在し、共に生き続けているからだ。
1658年〜古今を結び未来に繁ぐ
由緒正しき伝統の蔵
神の菌が息づく蔵
お酢を造る木桶は熊野古道に繁る熊野杉で作られた100年以上の年月を経た木桶が使用されている。
年月を経た木桶にはお米の発酵に欠かせない「神の菌」と呼ばれる「みふね菌」が奥底に呼吸をして息づいている。さらに、漆喰の壁でできた醸造蔵にも蔵付き菌が呼吸をし、のびのびと生きているという。
木の桶は菌が呼吸しやすく、120日以上かけてゆっくりと自然に発酵する。そして、お米からお酒へと変わっていく。そこから更に長い年月の間、呼吸を止めることなく発酵し、熟成させることによりお酢ができあがる。職人はその時の気温、湿度、そして菌たちの息吹を感じ、惜しみない労力と時間をお酢に捧げる。お酢はその職人の気持ちに応え、深い酷のある麗しい物になっていく。
こうして自然の発酵で長い時間かけて造られたお酢には、酢酸菌という菌の嬢王が存在する。酢酸菌が他の菌を静止させることができるため、防腐や殺菌の働きができるそうだ。
その話を聞いたとき、その昔、洗面器にお酢をいれて足をつけていた祖母を思い出した。「足を清潔に保つにはお酢が一番」と言っていた祖母の顔が浮かび、思わず口がほころんだ。
お酢は昔から殺菌力があり、除菌や消毒にも使われていた当時の記憶がよみがえる。
蔵元の想い
「並んでいるお酢の瓶たちに「がんばっていってこいよ」って声をかけて、瓶をなでるんです。お酢は生きてるし、感情もあるんですよ」と語るのは、四代目の中野社長。
中野社長が人生を費やし作り上げた米酢の入った瓶を見せてくれた。それは、こがね色の艶やかな輝きを放つほれぼれする逸品だった。わたしたちに見てもらおうと、中野社長の期待に応えて米酢は輝いたのかもしれない。
中野商店の代表商品は「黒酒酢R」。他のメーカで販売されている黒酢は「黒酢」の商品名だが、中野商店では「酒」の文字が黒と酢の間に含まれている。それは、「正しいお酢の造り方を表しているんですよ」と。この文字の並びから正しさを伝えようとしていた。
日本で作った玄米を100%使用し、まずはお酒にする。そして、お酒からお酢へと⋯。
お酢を造るのに、まずは玄米・米を作る米農家。今では貴重となった木の桶を造る木桶職人。日本の伝統的な蔵を造る蔵職人。そして、昔ながらのお酢を造る酢職人。
中野商店のお酢は日本の伝統文化とたくさんの職人の想いがつまった貴重なお酢であることには間違いがなかった。まさしく、それは国宝級だ。
そんな中野商店のお酢はどれも、ただただ酸っぱいだけではない。香り豊かで、ひとくち口にするだけで、酸味が口の中に広がり、だんだんと和らいでくる。
そして、奥から深い旨みが口いっぱいにひろがり、思わず「美味しい!」と自然に言葉に出た。こんな美味しいお酢は家に置いておきたいと思い、迷わず購入した。
儲かることが全てではない。
それは、私が職人あがりだから。
職人はいいものを造りたいだけ。
それが職人の心意気
と語った中野社長。
昔ながらの製法をやめることもできた、しかし職人の心意気を選んだ中野社長。
失うのは一瞬だけど、元に戻すことは二度とできない。便利な世の中になり生活が豊かになった一方で、大事なものが失われているのは確かだ。目まぐるしく変化するこの時代、中野社長は「私たちの目的は日本の伝統を後世に残すことであって、今の生活を豊かにすることではない。日本の伝統をいかに後世に繋げていけるかが今後の私の人生をかけてやるべき仕事です」という想いを話してくれた。
古き良き文化を継承する中野商店から、古いものを知らない世代は、それらを新しいものと感じ、新しいものはいつか古くなることをあらためて感じた。そのバランスをうまく繰り返して、後世へ引き継いでいってほしいと、私は中野商店のお酢を飲みながら強く願った。
神の仕え
八咫烏の導きをたどる
初代天皇である神武天皇は、熊野の神々の仕えと言われる八咫烏に熊野から吉野へと導かれ、橿原に朝廷を開き初代神武天皇となった。中野商店も、神の仕え八咫烏の導きと同じ道をたどる。熊野の野へ入り蔵を構え、吉野の野に入りさらに蔵を構える。そして、できあがった物を見せるため、世界のお披露目の舞台でもある京の都で店を構える。
店の語源は「見世棚」。自分の世界観を見せる場所に中野商店は京都を選んだのだ。
京都のまちは伝統や文化を重んじるが故の、他所から来たものを簡単には受け付けない厳かな空気がある。そんな京都の誇り高い意識をはねのけ、店を構えた中野商店。
それは日本の伝統を京都の地でお披露目できる自信が伝わったのだろう。
お披露目をする場を頂くだけでは義理が立たないのが職人というもの。
「今後は、京都の土地の由来したもので商品を造っていき、京都の生産者さんの期待に応えていきたい」と中野社長は述べた。
昔のものを大事にしながら、新しいものも取り入れ次の時代へ残していく。そして導かれた土地や人を愛す。そんな、中野社長の心意気が中野酢の人気の秘訣である。

-
株式会社 蔵元 中野商店
〒603-8408 京都市北区大宮北椿原町42
蔵:三重県南牟婁郡紀宝町
ご注文・お問い合わせ
TEL:075-205-5335 FAX:075-205-5336
ホームページ:https://nakanosu.co.jp/
中野酢公式オンラインショップ:https://nakanosu.com/
Instagram:https://www.instagram.com/nakanosu_official/
全国での催事出店の他、お取り寄せにも対応しております。